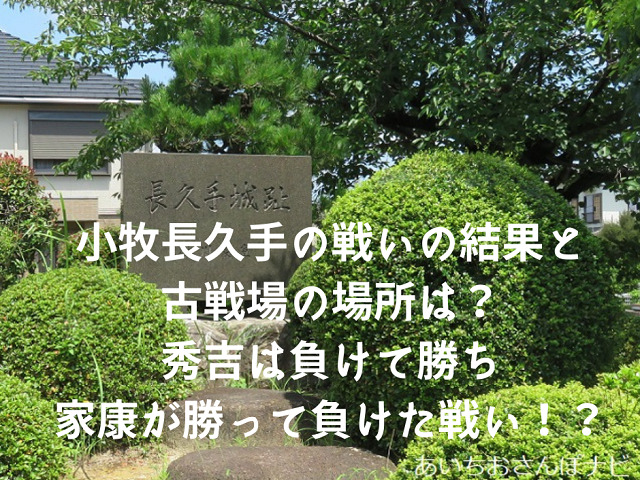織田信長が天下統一の手前で討たれ、戦国時代は混乱の時代に突入していきました。歴史って結果を知っていても、ドラマがあって面白いですよね。
着々と織田家家臣の中で台頭する羽柴秀吉と、不満を抱える信長の息子たちが対立、そして、秀吉対信長の息子&家康連合軍が対峙した、小牧長久手の戦いが始まりました。
この記事では、小牧長久手の戦いの勝敗の結果をわかりやすく、古戦場公園周辺に残る跡地についてご紹介します。
本能寺の変から2年後に起こった、秀吉と家康のもう一つの天下分け目の決戦は、負けた秀吉が天下を取るという、不思議な結果になっていきますよ。
小牧長久手の戦いの勝敗の結果は?

本能寺の変で織田信長が討たれた後、織田家の跡目相続を決める「清須会議」で、羽柴秀吉は信長の孫・三法師の後見人となって、他の家臣たちより優位に立ちました。
信長の三男・信孝は、織田家家臣の柴田勝家(信長の妹お市の方のだんなさん)を頼り、秀吉に戦いを挑むものの(賤ケ岳の戦い)、敗北。信孝も勝家もお市の方も亡くなってしまいます。
信長の次男・信雄(のぶかつ)は徳川家康を頼り、信雄・家康連合軍は秀吉に宣戦布告。家康は小牧城に布陣を敷き、土塁や砦を築いて、犬山城の秀吉と対峙しました。
小牧城と犬山城で膠着状態が続いていた時、秀吉側は「今この時に家康の本拠地、岡崎城を攻めたらいいじゃん」と、秀吉側の武将たちが4つに分かれて移動しました。
でもその情報は家康側にバレていたんですね。家康は兵を長久手に向かわせて、秀吉軍を壊滅的に追い詰めちゃいました。これが「長久手の戦い」です。
その後も小さな小競り合いが続き、3月から始まった戦いから8か月後、秀吉が織田信雄に和睦を申し入れます。
秀吉は多くの戦死者を出し、このまま戦いを続けたら負けるというタイミングで、「織田家の当主を三法師ではなく信雄さんにするよ」って信雄に耳打ちしたんです。

織田家当主になれる!と喜んだ信雄は、家康に無断で秀吉と単独講和を結んでしまいます。秀吉からみたら、信雄さんは扱いやすい(懐柔しやすい)人だったようです。
そして、秀吉はその場その場でうまくまとめる、世渡り上手な人だったんですね。
清須会議で織田家の跡継ぎは三法師と推し進めたのに、1年もたたないうちに信雄に替えちゃったんですから。
信雄が秀吉と和睦した以上、戦いが続けられない家康は撤退するしかなく、戦いには勝利したものの、秀吉の戦略に負けてしまったんです。
秀吉は戦いには負けたものの、うまく立ち回って、結局天下統一を果たしちゃいました。小牧長久手の戦いで勝った家康が、秀吉に服従する結果となったんです。
その屈辱が、秀吉亡き後におこった「大阪の陣」で秀吉の子・秀頼を自害させ、秀頼の子も処刑して豊臣家を断絶、豊臣方についた武将の追尾を10年以上続けたんだとか。
「絶対に許さない」という家康の怨念を感じますね…。
長久手の戦いの古戦場の場所は?
イオン長久手の西側にある古戦場公園に車を止めて、歩いて回りました(ぐるっと回って約3Kmくらいです)。
公園内にある長久手市郷土資料室で自転車を借りることもできますよ。
勝入塚と庄九郎塚、武蔵塚

古戦場公園の北には勝入塚(しょうにゅうづか)があります。勝入は、池田恒興(いけだつねおき)が晩年に入道(出家)したときの号(名前)です。
織田家の重臣だった池田恒興は、小牧長久手の戦いでは秀吉方として参戦、秀吉から「勝利の際には尾張1国を任せる」と約束されていたものの、徳川軍と戦って戦死してしまいました。
中央にある石碑は、明治24年に池田恒興の子孫が建立したものです。
住所:長久手市武蔵塚204
資料室受付時間:9:00~17:00
自転車の貸し出し時間:9:00~16:00
電話番号:0561-62-6230
駐車場:あり 普通車49台

古戦場公園の南には「庄九郎塚」があります。池田恒興の嫡男で岐阜城主だった池田元助(通称:庄九郎)も、父とともにこの地で戦死しました。
元助の弟・池田輝政(てるまさ)が家督を継ぎ、大垣城主、岐阜城主、吉田城主となったのち、姫路藩の初代藩主となって姫路城を現在の姿に改修したことは有名ですよね。
輝政は長久手の戦い後は秀吉に遇されて、家康の娘・督姫と結婚、秀吉が亡くなった後は石田三成と対立し、関ケ原の戦いでは家康方として参戦しています。
池田家は3英傑(信長・秀吉・家康)に家臣として仕えて名を挙げた、縁に恵まれた家系だったんですね。
住所:長久手市武蔵塚406

庄九郎塚を西へ行くと、「武蔵塚」があります。勇猛果敢で知られ「鬼武蔵」と呼ばれた森長可(もりながよし)の戦死地です。
秀吉方として参戦していた長可は、羽黒の戦いで徳川軍に敗戦し、白装束で決死の覚悟で出陣し、岩崎城を落とします。
けれども後ろに続く味方の軍が敗走し、池田軍とともに取り残された長可は徳川軍と激突、鉄砲で狙撃されて命を落としました。
住所:長久手市武蔵塚905
血の池公園と鎧掛けの松

武蔵塚から北西に行くと「血の池公園」があります。なんだか「血の池」って名前が不気味ですよね。
子供たちがサッカーを楽しめるグラウンドがある、緑のきれいな公園です。公園の半分は交通児童遊園になっていて、信号機や踏み切りが動いていました。
このあたりには池があって、家康方の武将が血槍や血刀を洗って、池の水が血で赤く染まったことから、「血の池」と呼ばれるようになったとのこと。

公園内には池はありませんが、公園近くに鎧(よろい)掛けの松があります。
池で刀や槍を洗う時に、武将たちが鎧をぬいで掛けたと言われている松です。現在の松は3代目、もみじの木とともに枝を広げています。
住所:長久手市城屋敷
長久手城趾

血の池公園近くに「長久手城趾」があります。徳川方の岩崎城主丹羽氏の家臣・加藤忠景(ただかげ)の居城でした。忠景は岩崎城落城した時に戦死しています。
長久手城も焼かれて廃城になりました。住宅街の中にポツンと観音堂とお地蔵さまが立っています。
観音堂には、長篠城が落城する前に埋めて隠した観音さまが、掘り起こされて祀られています。観音さまは、婦人病にご利益があると言われています。
住所:長久手市城屋敷2408
御旗山の富士浅間神社

御旗山(みはたやま)は、家康が金扇の馬印を立てたと言われる、小高い山です。現在は「富士浅間神社」が祀られています。
まだ新しい一の鳥居から、まっすぐ伸びる石段の階段が続いています。階段の途中にちょっと古いニの鳥居があり、さらに上った先に本殿があります。

富士社記によると、1584年の長久手の戦いから33年後1617年に創建、昭和60年に火災のため消失、平成3年に再建されたそうです。
地域の守護神として、特に子供の虫封じにご神威があると書かれていました。
子供の虫封じって、体内に虫がいるということではなくて、夜泣きなど訳もなく泣き出すことを抑えるってことですよね。
本殿前には「御旗山」と書かれた石柱が立っていました。
住所:長久手市富士浦
色金山で家康は天下をつかむ夢を見た
長久手市郷土資料館から北東に約1.8Km、車で移動して、色金山歴史公園の駐車場を利用しました。
色金山歴史公園

織田信長が討たれた2年後に勃発した「小牧長久手の戦い」、羽柴秀吉対織田信雄&徳川家康連合軍の戦いです。
その戦いの途中で秀吉方が「家康が小牧城にいる間に、家康の岡崎城を奪ってしまおう」という作戦を企てます。
けれどのその作戦は家康方に漏れていて、家康は小牧にいた兵を動かし、秀吉方の軍を追って進軍しました。
家康は長久手にある色金山(いろがねやま)に陣を張り、山頂にあった石を床机代わりに腰かけて、軍議を開きました。
家康軍は秀吉軍の先発隊(池田恒興(いけだつねおき)と森長可(もりながよし)の軍)を後続軍と分断し、壊滅させます。
後続にいた羽柴秀次(はしばひでつぐ:のちの2代目関白)は、岡崎城の襲撃を提案し、別動隊の総大将になるものの、徳川軍の奇襲に遭い、命からがら脱出しています。
戦いにキャリアのない秀次が、秀吉にいいとこ見せようと頑張ったけど、結局は足を引っ張って、秀吉軍の武将たちをたくさん討死にさせちゃったんですね。
大敗を喫した秀吉軍は戦力が半減、大きな痛手を被ったのでした。
現在、色金山は歴史公園として整備されています。展望テラスからは長久手市内が一望できます。ここで家康も同じように四方を見渡して、策を練ったんですね。
そして、この戦いを制して秀吉を失脚させたら、自分が天下を制することができるかもしれない、というひそかな夢を思い描いていたのかもしれません。

公園の中腹には長久手の合戦の慰霊碑だけでなく、日清戦争、日露戦争で命を落とした方たちの慰霊碑、大東亜戦争終結40年の慰霊碑などが並んでいます。
徳川方の武将・伴盛兼(ばんもりかね:信長の家臣でのちに家康に仕え、長久手の戦いで戦死)の墓碑もありました。
公園内は桜やもみじが植えられていて、桜や紅葉の季節にはまた違った風景が楽しめそうです。家康が馬に水を飲ませたという「馬泉水」も作られていました。
公園の駐車場近くには、国宝茶室「如庵(じょあん)」を模した茶室「胡牀庵(こしょうあん)」があり、250円(税込)で抹茶とお菓子がいただけます。
住所:長久手市岩作色金37-1
茶室:9:30~16:00(抹茶サービスは15:30まで)
茶室定休日:月曜日(祝日の場合は翌日)
駐車場:あり(普通車55台)
小牧長久手の戦いの首塚と安昌寺

色金山の麓に首塚があります。安昌寺の雲山和尚が長久手の合戦の戦死者を集めて、手厚く祀った塚です。
毎年合戦のあった日には花が手向けられ、法要が営まれていたそうで、江戸時代には尾張藩士の姿も見られたそうです。
ちょっと細い一方通行の道沿いで、駐車スペースがないので気を付けてくださいね。

首塚から県道57号線を挟んだ北側に安昌寺(あんしょうじ)があります。山門前には大きな薄墨桜がありました。樹齢30年ほどなんだとか。
桜の季節にはきっとたくさんの人の目を引き付ける桜なんでしょうね。

山門の正面には本堂、左手に観音堂があります。観音堂には平安時代の木造十一面観音坐像が祀られていて、100年に一度開帳されます。次回は2080年なんだとか…。
安昌寺には尾張藩士をはじめ多くの藩士が訪れ、合戦の書付を残しています。うわばみ(大蛇)の伝説の絵馬などの美術品も伝わっています。
住所:長久手市岩作色金92
首塚
住所:長久手市岩作元門42
家康が戦勝祈願した教圓寺

色金山で軍議を開いた家康は、秀吉方の様子をうかがいながら、御旗山(みはたやま)へ進軍しました。
その途中、旧岩作街道沿いにある教圓寺(きょうえんじ)のご本尊、阿弥陀如来に戦勝祈願をしたと言われています。その時に家康が寄進したと伝わる葵の紋付陣羽織が残されています。
江戸時代には寺子屋が置かれていたこともあり、境内には筆塚も残されています。現在はお隣が「さつき幼稚園」になっています。
住所:長久手市岩作東島103
・岩崎城の歴史を歩く!16歳の武将が家康を救った小さな城の大きな物語
・名古屋市守山区の龍泉寺は城があるねこ寺!御朱印とアクセスと駐車場は?
・小牧山城の石垣は信長が築き家康が改修?見どころとアクセス駐車場は?
・犬山城の観光おすすめスポットと歴史は?御城印や名城スタンプはある?
さいごに
1584年におこった小牧長久手の戦いの結果と、古戦場公園周辺に残る跡地についてお伝えしました。
長久手の戦いの合戦跡地を巡るなら、色金山歴史公園と古戦場公園を起点にして徒歩、またはレンタサイクルでまわるのがおすすめです
この戦いで常に優位に立って勝利をおさめた家康でしたが、結果的には秀吉が家康を傘下に入れて、信長の後継者として政権を確立させます。歴史って、知れば知るほど面白いですね。
長久手古戦場の跡地は、住宅地の中でひっそりと歴史を物語っています。長久手合戦史跡巡りをぜひ楽しんでみてください。あ、でも、暗くなるとちょっと怖いから、明るいうちに巡ってくださいね。
・ジブリの大倉庫には何がある?見どころ楽しみ方とカフェやお土産をご紹介!
・ジブリパーク無料エリアの忘れ物とチケットなしでも行けるお土産売り場はココ!
・トヨタ博物館のアクセス駐車場と入館料金は?ガイドツアー参加がおすすめ!